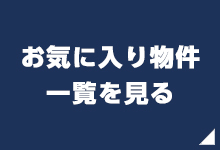第21話 住宅用太陽光発電「2019年問題」を再考する

昨年末から住宅用太陽光発電の「2019年問題」は、この業界を少しだけ賑わせた。このコーナーの読者にはあらためて説明するまでもないが、念のため簡単に説明すると、2009年に導入された住宅用太陽光発電(10kW未満)の余剰電力の固定買取期間が10年で、2019年にはいよいよその買取期間の終わりを迎える住宅用太陽光発電が40万件の規模で大量に生まれる。その取り扱いを巡る議論を「2019年問題」という。
この問題について、去る5月22日に経産省から出された「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会‐中間整理」の中で、「①電気自動車や蓄電池と組み合わせることなどにより自家消費をすることや、②小売電気事業者やアグリゲーターに対し、相対・自由契約で余剰電力を売電することが基本」とし、「一般送配電事業者による引受けはあくまで一時的・例外的な措置」としている。自家消費や相対・自由契約を活発化させるという、この基本的な方向は、ポストFITの観点から良いだろう。今から、新しいビジネスモデルを準備し、期待を高めている事業者も多いことだろう。 他方、後段の一般送配電事業者による引受けについては、「一般送配電事業者は売り手と買い手が決まっている電気を運ぶこと(託送供給)をその業務とするものであるとともに、買い手不在の余剰電力は周波数調整の負担を増す可能性があることも踏まえれば、一般送配電事業者による引受けは無償とすることが適当」としている。この「一般送配電事業者による引受けは無償」との方針は、公共政策の観点から問題が大きい。
第1に、40万件もの一般家庭が取りこぼしなく自家消費や相対・自由契約に移行できるとは、およそ考えにくい。しかも、これは事業者同士の取り引き(BtoB)ではなく、一般家庭を対象とする取り引き(CtoB)であり、知識や情報の大きな非対称がある。こうした場合には、公共政策の観点から、必ず「最後の救済策」(ラストリゾート)を用意する必要がある。
第2に、明らかな有価物(電気及び環境価値)を無償で引き取るというのは、経済や商行為の大原則に反する。一般送配電事業者の「周波数調整の負担」が増すかもしれないが、それは太陽光発電の余剰電力だけが追うべきコストではない。他方で、昼間ピークを削減する電源として有意なkW価値もあり、累積では、必ず化石燃料を減らし、CO2も減らす効果がある。
第3に、こうした無償引き受けを定めることは、再生可能エネルギーを拡大してゆく政府の方針に反して、今後の新たな家庭用太陽光発電の普及に水を差しかねない、間違ったメッセージを社会に発信することになる。そもそも再生可能エネルギーは、純国産エネルギーでCO2を減らし、原発依存度も減らす、もっとも優先すべき電源であることを前提とすべきである。
第4に、「一般送配電事業者は売り手と買い手が決まっている電気を運ぶこと(託送供給)をその業務とする」という認識は、現時点の過渡的なものでしかない。本来、所有権分離を含む完全発送電分離を実現した場合には、一般送配電事業者は「プール」のようなかたちで電力を引き受ける役割となるべきであり、その時、再生可能エネルギーは、上記の原則に沿って、最優先で流れ込むべき電源である。
第5に、こうした措置は、今後、全量売電の再生可能エネルギーの「FIT後」にも間違った、「悪しき前例」となる。
では、どの程度の価格で買い取るべきか。本来なら、卸電力価格プラス環境価値、または回避可能原価プラス環境価値が妥当であろう。最低でも、電力会社が節約される燃料費代プラス環境価値は、支払うことは必須だろう。経済産業省は、速やかに中間報告の答申を見直すべきではないか。